
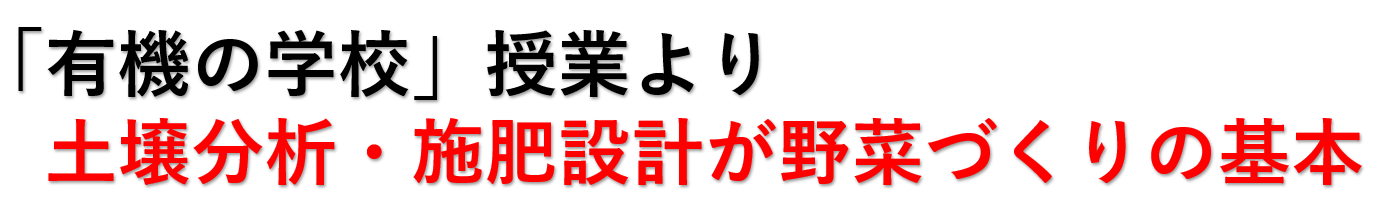

研修生一人ひとりが土壌分析をおこないます。

土壌分析の成分を抽出して試薬を注入

土をフルイにいれ振るう
6月の授業では土壌分析・施肥設計を行いました。経験と勘によって栽培された畑は、過剰施肥によって土壌中の養分バランスが崩れていることがあります。BLOF理論で栄養価の高い美味しい野菜を作るためにも、土の中身を知る土壌分析と、作物に合わせた畑の施肥設計が必須です。
また、過剰施肥は土壌だけでなく河川や地下水の汚染を招くことになるため、環境に配慮した適量な施肥を行うためにも土壌分析・施肥設計は大切です。
今回、研修生それぞれが自分の畑の土を持ち寄り、土壌分析キットを用いて土壌分析を行いました。
➊ 初めに土をふるいにかけ、専用の試薬と器具を使い土壌から養分取り出す、「抽出」という作業を行います。
➋ 抽出した養分が溶け込んだ溶液を試験管に移し、試験管毎に専用の試薬を添加して発色させます。
➌ そして、発色度合いを専用の装置を使って読み取ります。
➍ その後、測定値を施肥設計ソフトに入力し、実際の畑にどれだけの肥料を撒くか算出します。
作物によって必要な養分が違うため、作物に合わせた施肥設計が必要です。就農して2~3年すると栽培に慣れて土壌分析せずに、勘を頼りに施肥設計をして栽培に失敗することがあります。結果的に原因がわからずに同じ失敗を何度も繰り返すことになるので、必ず栽培の基本に土壌分析・施肥設計を位置付ける必要があります。

山都町は元々有機農業の取り組みが盛んな地域というイメージがありました。そのような地域で若いスタッフ中心に販売業のプロ、生産現場のプロが協力して有機農業を学べる場所ができたことは理想的なことだと思います。とてもフレンドリーな空間で誰でも参加しやすい明るい学び場にお招きいただき感謝しています。
研修生の経歴も様々なので授業ではこちらが教える立場ですが、休憩時間は逆にこちらが色々教えて頂いたり学びの刺激にあふれた時間をいただきました。 今後の活動も楽しみにしています!!ありがとうございました!!

浅野健治 先生
(株)ジャパンバイオファーム所属
JOFA公認BLOFインストラクター
ORGANIC SMILE理念】私たちは この地球の生命の息吹が有機的に響きあい SMILEできる未来を創造します。

ORGANIC SMILE ファーマーコース研修生 黒坂克三
4月に大阪から山都町へ夫婦で移住した黒坂克三と申します。就農を目指して、有機の学校で学んでおり、現在、学校の圃場にて小松菜栽培を行っています。小松菜は生育が早く繰り返し栽培が出来るため、栽培技術を習得するには良い作物だと思い、小松菜栽培を開始しました。
1回目の栽培は7月中旬に収穫しましたが、予定の約半分しか収穫できませんでした。雑草の成長に小松菜が負けた事、アブラムシの発生により収穫できなかった畝がありました。原因は❶潅水配管の不具合に気づくことができず水を十分に与えられなかった事、❷圃場の雑草管理が出来ていなかった事が挙げられます。
2回目は7月下旬より、学校で学習した土壌分析・施肥設計を行い、トラクターで耕耘、太陽熱養生処理を行いました。8月末に播種しましたが、播種機にかける力のバランスが悪かった為、畝の中央は芽が出ていない箇所か多かったです。播種が確実に出来ていないと、何も育てられないと実感する事ができました。

黒坂克三さん

水浸しとなった実習圃場
それだけ重要な工程であり、この技術を早く習得したいと思います。播種後、防虫ネットを張り、潅水配管の不具合を修理し、また畝間および圃場内の除草をし、虫の住処を出来る限り少なくしました。完全に虫食いを防ぐ事は出来ませんが、順調に本葉の数も増え、葉も大きくなってきました。
しかし、こんな時に台風14号が発生。最大級クラスの台風と聞いて、小松菜が折れてしまうのではないかと心配しました。確認後、8畝の内1つの畝の防虫ネットが剥がれていました。この圃場は木々に囲まれているため、この程度の被害で済んだと思っております。もう台風は来てほしくありませんが、自然現象はどうにもならない事を実感しました。小松菜は現在約20㎝まで成長しており、近々収穫を行う予定です。
今回は2月のオーガニック エコ フェスタの栄養価コンテストへの参加も考えており、どういう結果になるか、非常に楽しみです。引き続き栽培の知識を増やし、栄養価の高い有機野菜を作り、販売出来る様に頑張りたいと思います。
出典:山の都はワンダーランドから掲載
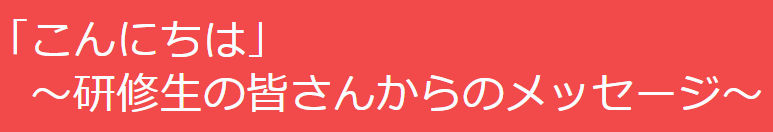
5年前に夫婦で就農して小松菜・ほうれん草を栽培していました。経営も厳しく農業を続ける事が難しくなり夫は離農してしまいましたが、私は農業を続けたいという思いを捨てきれずにいました。
農業は、暑さ寒さや女性にとって体力がつづかず大変な事の方が多いのですが、野菜たちは手をかければかけただけ応えてくれます。時には害虫被害や病気に悩まされる事もありますが、元気に育った野菜たちを収穫するときは、とてもうれしく、やっててよかった~って思います。
今はCOGの農場で農業を続けていますが、将来再就農をめざして、有機の学校で栽培はもちろん、農機具の使い方・メンテナンスの方法・農業経営などを改めて学んでいます。

東家智美さん

成瀬幸輝さん
熊本県の阿蘇市で兼業農家を行っている成瀬です。2023年から農業にどっぷり漬かっていこうかと思っています。私たちの周りでも高齢により山間部の農地の管理ができなくなり耕作放棄地や、山林になってきているところが多くなってきています。そんな狭小でひょごどる農地を生かしつつ、今ある農地で持続可能な農業を行っていくことはできないかと考えていました。そんな中で有機の学校ORGANIC SMILEが2022年に開校するとの話を聞き入学しました。有機農業の知識は皆無でしたが、基礎からの有機農業やBLOF理論などを学び今後の営農で実践することで持続可能な農業へ一歩でも近づけたら思っています。

※ひょごどる:熊本弁でゆがんでいる、変形しているの意味
